ステゴサウルスとは
| 学名(属名) | Stegosaurus |
| 名前の意味 |
屋根のあるトカゲ
stegos(屋根)[ギリシャ語]-saurus(トカゲ)[ギリシャ語] |
| 分類 | 鳥盤目・装盾類 (装盾亜目・剣竜下目) |
| 全長 | 約7m |
| 食性 | 植物食 |
| 生息時期 | ジュラ紀後期 |
| 下分類・種名 |
Stegosaurus stenops
(模式種)
※かつて多くの種が記載されたが、現在有効とされるのはStegosaurus stenopsのみとする説が有力。 |
| 論文記載年 | 1887 |
| 記載論文 |
A new order of extinct Reptilia (Stegosauria) from the Jurassic of the Rocky Mountains.
American Journal of Science(Series 3 Vol. 14), by Marsh, Dec, 1887. |
特徴
ステゴサウルスの最大の特徴は、"背中に並ぶ板状の骨"と"尾先に並ぶ4本のスパイク"です。

背中の板は、骨の芯の周りを血管が豊富な皮膚が覆う構造になっていました。その役割は、単一ではなく、複数の目的を兼ねていたと考えられています。主な役割は、仲間を見分けたり、異性に求愛したり、ライバルを威嚇したりするための視覚的なディスプレイであり、その派手な見た目を維持するために、副次的に体温調節(熱を逃がす)の機能も果たしていた、という説が現在では最も有力です。防御用の鎧としては、あまり役に立たなかったようです。
また、成体になって身体の成長が止まった後も、背中の板は大きくなり続けていたことがわかっています。

尾の先には、60cmにもなる2対4本のスパイクがあります。肉食恐竜から身を守るための武器でした。ステゴサウルスのスパイクにぴったりはまる穴のあいた、アロサウルスの腰部化石が発見されているのです。ステゴサウルスを襲ったアロサウルスが、強烈な反撃を受けたことを物語っています。
このスパイク、子どものころにはスポンジ状でもろい構造をしていましたが、大人になるにつれて堅く緻密質な構造に変化していったことがわかっています。
サゴマイザーの誕生
ステゴサウルスの尾のスパイクには「 サゴマイザー (Thagomizer) 」という愛称がありますが、これは科学論文ではなく、1982年にある有名なギャグ漫画(ゲイリー・ラーソン作『ファー・サイド』)から生まれました。作中で、洞窟の壁画を説明する原始人が「この武器は、今は亡きサグ・シモンズにちなんで"サゴマイザー"と呼ばれている」と語ったジョークが元ネタです。古生物学者たちがこのユニークな名前を気に入り、現在では論文などでも使われる一般的な用語となっています。

首の喉部分には細かい骨が並んでいます。弱い部分を守る防具の役目を果たしたのでしょう。
ステゴサウルスの噛む力
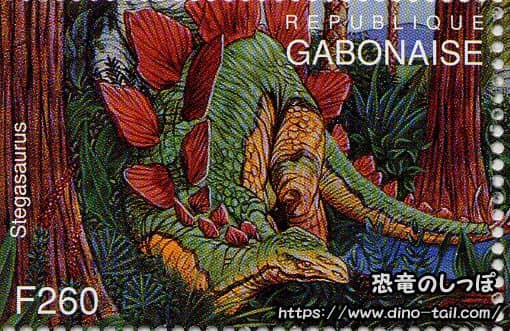
背中の板で体温調節を行い護身用の武器-スパイクももつ機能的なステゴサウルスでしたが、弱点もありました。
噛む力が極端に弱いのです。
2010年カナダ・アルバータ大学で、ステゴサウルスの噛む力についてコンピューターを使った解析が行われました。ステゴサウルスの噛む力は、前歯付近で140N(ニュートン)、奥歯でも275Nほどだったことがわかりました。人間の噛む力は750N、オオカミでは1400N。ひとの3分の1ほどの噛む力しかなかったことになります。
ステゴサウルスの主食は、背の低い(柔らかい)シダ植物だったようです。もしステゴサウルスが現代に生息していたとしても、草原に生えている硬いイネ科の植物を食べることはできなかったでしょう。
背中-骨板の大きさの違いは性差?

2015年、ステゴサウルスの背中-骨板の大きさとオス・メスの性差の関係について触れた論文が発表されました。
アメリカ・モンタナ州の同一場所で発見された5体のステゴサウルス。5体の背中の板は、明らかに「幅広」と「幅狭」に分類されたそうです。幅広の骨板面積は、幅の狭いものより45%も大きかったのです。どちらがオスでどちらがメスかはわかりませんが、背板の幅の違いは性差によるものである可能性を示唆しました。
第2の脳を持つ説

ステゴサウルスには、脊髄が通っている背中に大きな空洞があります。
かつて、その部分に「第2の脳」を持つ説がありました。
頭部の脳があまりにも小さく(クルミの大きさ程度)、「大きな身体を制御するために、別の場所にも脳があるのでは?」と考えたからです。
現在では「第2の脳」説は否定され、背中の大きな空洞は「神経に栄養を送るためのグリコーゲン体が入っていた場所」と考えられています。
奇跡の標本「ソフィー」が明かす真実

長年、ステゴサウルスの全体像は、断片的な化石を組み合わせたものでした。しかし2014年、ロンドン自然史博物館は、 約85%の骨が揃った、史上最も完全なステゴサウルスの標本 を公開し、世界を驚かせました。この標本は「 ソフィー(Sophie) 」という愛称で知られています。
「ソフィー」の詳細な研究により、これまで謎だった多くの点が明らかになりました。
- 姿勢: 首はしなやかに動きましたが、頭は常に地面に近く、背の低い植物を食べる「低位置採食者」であったことが確実となりました。
- 体重と歩行: 生きていた時の体重が正確に計算され、その歩行速度は人間の早歩き程度(時速約6km)と、非常にゆっくりであったことが示唆されています。
- 性差: 「ソフィー」の骨板は背が高く幅が狭いタイプで、これがオスとメスのどちらの特徴なのか、今後の研究の重要な基準となっています。
「ソフィー」は、ステゴサウルスの生物学を解明するための、まさに「基準となる一個体」として、現在も研究が進められています。
初めての論文記載と復元図の変化
ステゴサウルスの名前が初めて論文に掲載されたのは、1877年のことです。古生物学者マーシュMarshが1877年12月のAmerican Journal of Science(Series 3 Vol. 14)の中で、論文"A new order of extinct Reptilia (Stegosauria) from the Jurassic of the Rocky Mountains."を発表しました。この論文で、アメリカ・コロラド州モリソン層北部から発掘された断片的な化石にもとづいて、"ステゴサウルスStegosaurus armatus"が記載されます。

ステゴサウルスは当初、水棲カメのような爬虫類と考えられていました。背中の板も、現在復元されているように立てられたものではなく、カメの甲羅や屋根瓦のように横倒しになった状態で背中を覆ったものとして扱われていました。属名Stegosaurusはギリシャ語で「屋根のあるトカゲ」の意味です。この"屋根"に由来しています。
その後さらに保存状態の良い背板化石が見つかったことで、1891年までには現在のような背板が立った状態で並んでいるステゴサウルスを描くようになっています。
初めて記載されたステゴサウルスは"Stegosaurus armatus"でしたが、残された標本は断片的で、種を特定するための比較標準標本とするには適していませんでした。そのため、2013年の動物学命名法に関する国際委員会によって、ステゴサウルスのタイプ種は"Stegosaurus armatus"に代わって、より保存状態の良い"Stegosaurus stenops(標本番号USNM 4934、1887年に記載)"に置き換えられています。
ガチャピンとステゴサウルスの関係

日本のヒーロー"ゴジラ"の背中に生えたヒレは、ステゴサウルスの背板がモチーフになっています。
また、2012年福井県立恐竜博物館の協力により、ポンキッキシリーズで活躍した"ガチャピン"の祖先は<鳥盤目-装盾亜目-剣竜下目>と推定されています。
