コンカベナトール(コンカヴェナトル)とは
| 学名(属名) | Concavenator |
| 名前の意味 |
クエンカのハンター
Cuence(スペインのクエンカ県の)[地名]-vēnātor(ハンター)[ラテン語] |
| 分類 | 竜盤目・獣脚類(獣脚亜目・テタヌラ類アロサウルス上科) |
| 全長 | 約6m |
| 食性 | 肉食 |
| 生息時期 | 白亜紀前期(約1億2500万年前) |
| 下分類・種名 | Concavenator corcovatus |
| 論文記載年 | 2010 |
| 属名の記載論文 |
A bizarre, humped Carcharodontosauria (Theropoda) from the Lower Cretaceous of Spain.
Nature 467 (7312): 203–206. Ortega, F.; Escaso, F.; Sanz, J.L. , 2010. |
特徴

コンカベナトールは、スペインのラス・オヤス(Las Hoyas)でほぼ全身が保存された状態で発見されました。獣脚亜目に属する恐竜です。
名前の意味は、発見地スペインの地名にちなみ"クエンカのこぶのあるハンター"。日本語では、コンカベナトル、コンカヴェナトルと表記されることもあります。
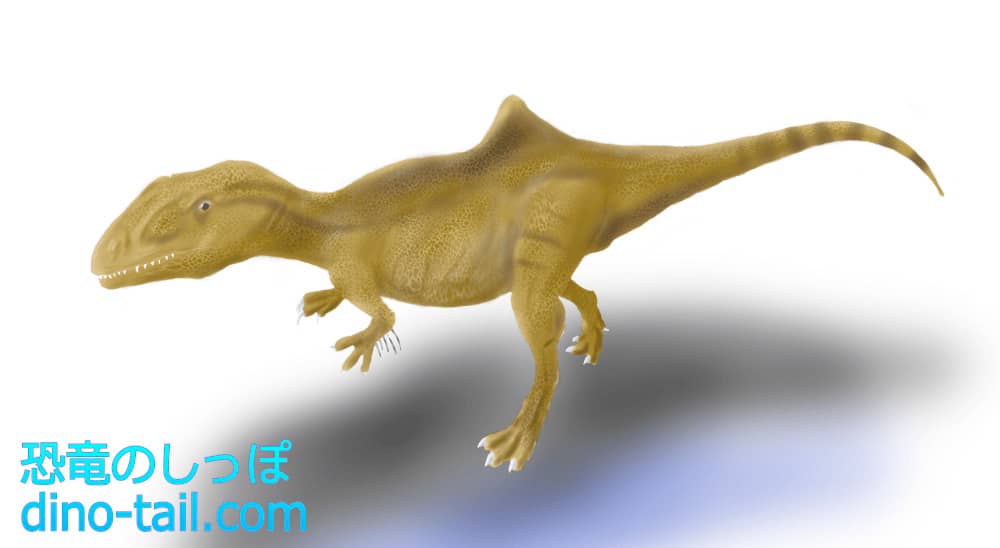
コンカベナトールの全長は約6m、背中の後方にこぶのような盛り上がりをもつ珍しい恐竜です。
胴椎(背骨)は計13個。完全に関節されていた状態で見つかっています。後方2つの胴椎(第11と12)では神経棘が極端に長く、第10胴椎の約2倍以上の長さがありました。この奇妙な構造が何のためにあったのか、いくつかの説が提唱されています。
- ディスプレイ説: 仲間を見分けたり、異性に求愛したりするための「見せる」ための器官だったという説です。生前は皮膚に覆われ、鮮やかな色をしていた可能性も考えられます。
- 体温調節説: ラクダのこぶのように脂肪を蓄え、エネルギーを貯蔵したり、体温を一定に保ったりするのに役立ったという考え方です。
現在のところ、どの説が正しいのか結論は出ていませんが、このユニークなこぶがコンカベナトールの生態において重要な役割を果たしていたことは間違いないでしょう。
後脚(後肢)は、関節が外れているものの完全に残されていました。右後脚(後肢)には、一部皮膚の軟組織も保存されています。
アロサウルス上科カルカロドントサウルス類に属しています。
腕に羽毛の痕跡?鳥類との意外な共通点
コンカベナトールの化石を詳細に調査したところ、前腕の骨(尺骨)に、小さなこぶのような突起が並んでいるのが発見されました。これは「クイルノブ(羽軸突起)」と呼ばれる構造で、現生の鳥類では、風切羽のような大きな羽の軸を骨に固定するために存在します。
この発見は、コンカベナトールの腕にも、原始的な羽毛、あるいはそれに似た構造物が付着していた可能性を示唆しています。もちろん、コンカベナトールは空を飛ぶことはできませんでしたが、この羽毛状の構造は、求愛のディスプレイや腕の保護に使われたのかもしれません。
議論の的: この突起が本当にクイルノブ(羽軸突起)なのかについては、一部の研究者から疑問も呈されており、現在も議論が続いています。しかし、もしこれが羽毛の痕跡であれば、カルカロドントサウルスのような大型の肉食恐竜の系統で羽毛の存在を示す、最も初期の証拠の一つとなり、恐竜の進化を考える上で非常に重要です。
白亜紀のラス・オヤス(Las Hoyas)

コンカベナトールが生息した当時-白亜紀前期(約1億2500万年前)のラス・オヤスは、亜熱帯気候の湿地帯だったと考えれています。エビやワニ形類、魚類などの水棲生物を中心に、昆虫やトカゲ、鳥類の多様な化石が発見されています。
この地が大型獣脚類コンカベナトールのなわばりだったとすれば、生態系の頂点近くにいたのでしょう。
コンカベナトール(コンカヴェナトル)の切手・化石ギャラリー



